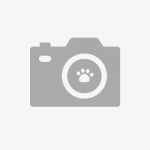愛犬の避妊をするかお悩みの飼い主様へ。後悔しない選択をするために。
愛犬の避妊を検討している飼い主様にへ。メス犬の避妊には、心身両面からメリットもあれば、デメリットも存在します。それらを知っていただき、あとで後悔しないような選択をして頂ければと思っております。
- 更新日:
避妊手術のメリット・デメリットとは?
大切な愛犬に避妊手術を受けさせるべきか?メス犬の飼い主様であれば、まず考えなければならないことかもしれません。
避妊手術は、愛犬の望まない妊娠を防ぐだけでなく、乳腺腫瘍、子宮蓄膿症などのホルモン依存性の疾患にかかるリスクを軽減したり、また初回発情より前に手術を行うことで乳腺腫瘍の発生も抑えられることが報告されており、避妊は愛犬が将来病気にかかることを防ぐ上で有効な選択肢の1つと言えます。
一方で避妊手術をすると、性ホルモンの分泌バランスが崩れるため、食欲が増進したり代謝カロリー量が減少して太りやすくなるというデメリットがあります。手術後、体重の増加が見られる場合には、フードの量を調整したり、フード自体を低カロリーでダイエット用タイプに切り変えたり、運動を積極的に行うようにしましょう。
また、避妊手術は、よく行われれているとは言え外科手術ですので、愛犬の体への一定の負担やリスクは生じます。特に避妊手術は麻酔をかけて行います。もちろん事前に血液検査などを行い麻酔を使用しても問題なさそうか必ずチェックされますが、愛犬の年齢・健康状態によっては麻酔によるトラブルが生じる可能性はゼロとは言えません。
愛犬の状態も踏まえて、獣医師と相談の上、手術を受けるか判断いただければと思います。
愛犬にとって大切な手術時期
飼い主は、愛犬にどのタイミングで避妊手術を受けさせたらいいのか、ベストな時期はいつなのかと迷うことでしょう。一般的には、最初の発情を迎える前が理想的とされています。
犬種による差や個体差はありますが、初めての発情は生後6〜8カ月くらいに起きると言われています。
すべての犬に当てはまるわけではないので、個々の犬に合わせて手術の時期を検討する必要性がありますが、初回発情前に避妊手術をすることで、乳腺腫瘍の発生率がかなり抑えられると言われています。
仔犬を家に迎えた飼い主は、早めにかかりつけの病院を見つけて相談をするのが良いでしょう。愛犬の状態により、避妊手術に適した時期は違ってきます。
あまりに早いタイミングで避妊手術を行うと尿失禁を発症する可能性があるので、獣医師と相談しながらベストな時期を検討しましょう。

気になる手術の内容
犬の避妊手術は、動物病院にて全身麻酔で行われます。開腹手術で卵巣のみを摘出、または卵巣と子宮の両方を摘出する2つの手術方法があります。一般的には、子宮内に膿がたまる子宮蓄膿症という病気の予防を含めて子宮も摘出する(子宮卵巣摘出手術)ことが多いですが、子宮蓄膿症は卵巣から分泌されるホルモンが影響しているため、卵巣を取ることで子宮蓄膿症も十分に予防できるとも言われていますので、獣医師に相談し、愛犬にとってベストな方法を選択してあげれたらと思います。
手術を受ける際は、術前検査をしっかり行ってもらい、術後は、開腹手術となるため1~2泊することになります。術後の回復状況によっては延泊もあります。健康状態に問題がないと獣医師が確認できれば、連れて帰ることができます。
手術後のケア
手術が終わり、病院からお迎えOKのお電話をもらったら、いざ愛犬のもとへ。術後は傷口の経過観察が大事です。術後に痛みが残ったり、傷口が開いてしまうことは基本的にはありませんが、エリザベスカラー(ネッカー)等が取れてしまい、犬が傷口を舐めてしまうと話は別です。エリザベスカラー(ネッカー)があることで食事をうまく食べられないというような場合は、術後着を着用させることもあります。
抜糸は、一般的には手術後7日~10日ほどで行われます。抜糸までの間は病院で処方される抗生剤や消炎剤を内服させることになりますが、基本的には普段通りの生活をして構いません。
避妊手術を行うと、ホルモンバランスの変化などにより太りやすくなるため、摂取カロリーを通常の3割ほど減らした方がいいといわれています。避妊手術をした犬用の低カロリーフードもあるので、獣医師に相談してみましょう。
動物医療センターPecoでの避妊手術のご案内

動物医療センターPecoは、渋谷区、原宿に2021年8月に開設した、全5フロアの犬と猫の動物病院です。
「動物の生涯に寄り添い、見守り続ける医療施設でありたい」というビジョンを掲げております。
大事な愛犬の避妊のお悩みなら、当院にご相談ください。
麻酔の安全性を高めるための手術体制
犬の避妊手術には、全身麻酔が必要となります。
動物医療センターPecoでは、手術中での麻酔の安全性を高めるために、執刀医に加えて、麻酔に習熟した獣医が麻酔を行う体制で臨んでおります。
麻酔の方法は、吸引麻酔(気道にチューブを挿入し、酸素と麻酔ガスを注入する方法)を選択しております。メリットとして、呼吸の経路が管理しやすく、事故のリスク(例えば、呼吸が止まり、酸素が体の中に取り込めない、といったリスク)を低下させることができます。
また手術中は、わずかな状態の変化も見逃さないように、心電図、血圧、体温、体内の酸素、麻酔の深さを、各種のモニターで管理しており、なにか変化があった場合は、すぐに対応できる体制で臨んでおります。
手術後のご不安をご自宅からご相談できる見守り体制

手術が終わったあと、ご自宅で何か変化があるか、ご心配な飼い主さまもいらっしゃるかと思います。
動物医療センターPecoでは、ご自宅などで、通常とは異なる変化が気になった際には、スマートフォンから病院スタッフに報告・相談頂けるように、見守り体制を用意しております。
ご自宅から病院に行くべきかどうかの判断を早期に行うことができることで、移動による動物と飼い主様の負担を、少しでも減らしたいと考えております。
当院へのご相談はこちら
当院へのアクセスは原宿駅から徒歩4分。病院裏に無料駐車場もございます。
ご予約は、Web予約もしくはお電話にて承っております。
皆様の大事な家族にとっての「動物の生涯に寄り添い、見守り続ける医療施設」となれれば幸いです。
動物医療センターPecoの詳細はこちら